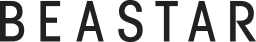2025.07.22

企業のSNSアカウントは今や、企業の広報・採用・販売促進において欠かせない存在です。
顧客と直接繋がってファンを増やし、売上を向上させる非常に強力なツールになり得る一方で、炎上・誤解・運用停止などのリスクに直面するケースも。
たった一度の不適切な投稿が、長年かけて築き上げたブランドの信頼を瞬時に失ってしまうような“諸刃の剣”であることも忘れてはなりません。
「うちの会社の運用方法は、本当にこれで大丈夫だろうか?」
「もし炎上してしまったら、と考えると不安でつまらない企画になる」
「間違った運用でブランドを損なっていないか不安……」
このようなお悩みを日々のコンサルティングの中で数多く耳にします。
攻めのマーケティング施策に目が行きがちなSNS運用ですが、実は成果を出し続けている企業ほど「守り」、すなわちリスク管理を徹底しています。
この記事では、企業のSNS担当者様が絶対に知っておくべき注意点をプロの視点から徹底的に解説!最後まで読めば、SNSに潜むリスクを網羅的に理解でき、明日から何をすべきかが明確になります。
企業のSNSのリスク管理が重要なワケ
SNSは個人向けの自由な発信ツールとして発展してきた背景があります。
そのため、企業アカウントとして運用する際は、“ブランド”や“組織”としての責任を伴う発信であることを忘れてしまいがちです。
ですが企業のSNSでは、一度の投稿が以下のようなリスクにつながる可能性もあります。
- 炎上によるブランドイメージの毀損
- 法令違反による削除やペナルティ
- 意図しない誤解・炎上での信用失墜
- 広報と現場で認識がズレることによる混乱
- リソース不足によるアカウントの形骸化
こうした事態を未然に防ぐには、SNSの特性を理解したうえで社内体制・ルール・投稿内容の設計を行う必要があります。
企業のSNSアカウントにおける4パターンの失敗事例

「自分たちは大丈夫」と思っていても、落とし穴は思わぬところに潜んでいます。
まずは、実際に起きた失敗事例のパターンから、リスクの重大さを学びましょう。
①モラル欠如型
特定の層を差別するような表現、災害や事件に関する不謹慎なジョーク、担当者の個人的な思想の投稿など、企業の公式アカウントとして不適切な発言で大炎上するケース。
最も多く、そして最も致命的な失敗パターンです。
投稿内容ではなく、企業のPRや広告の内容自体が時代錯誤である場合や、ターゲットにとって適切でない場合などに炎上するケースも。
SNS担当者だけでなく、全社的な認識のアップデートが必要だと言えるでしょう。
②情報漏洩型
発表前の新商品情報、顧客の個人情報、社外秘の資料などが、投稿写真の背景にうっかり映り込んでしまい、情報が漏洩するケースもあります。
企業の信用問題に直結し、最悪の場合は訴訟につながる可能性もあるため注意が必要です。
③権利侵害型
インターネットで見つけた他人のイラストや写真、好きなアーティストの楽曲、あるいは名称などを、許可なく投稿に使用してしまうケース。
著作権や肖像権の侵害にあたり、損害賠償問題に発展する可能性もあります。
個人アカウントでは「グレー」とみなされるようなことも、企業アカウントだと特に気をつけなければなりません。
④ステマ型
ステマ(ステルスマーケティング)とは、広告であることを隠して、あたかも第三者の口コミであるかのように商品やサービスを宣伝する投稿のこと。
2023年10月から景品表示法で明確に禁止され、発覚すれば企業の社会的信用は地に堕ちるでしょう。
依頼先の芸能人やインフルエンサーにも迷惑をかけることになります。
これらの失敗は、ブランドイメージの低下、顧客離れ、売上減少、そして場合によっては株価の下落といった深刻な事態を引き起こします。
SNS運用におけるリスク管理は、もはや「やっておいた方が良い」ではなく「やらなければならない」必須事項です。
【運用“前”編】アカウント開設前に固めるべき3つの土台

炎上を防ぐためには、運用を始める前の「土台作り」が最も重要です。
以下の3つは必ず設定しましょう。
SNS運用の「目的」を明確にする
まず最初に、「何のためにSNSを運用するのか」という目的を明確に言語化しましょう。
【目的の例】
- ブランドの認知度向上
- 商品やサービスへの理解促進
- 集客、問い合わせ・予約の増加
- ECサイトへの送客、売上アップ
- 顧客との関係構築、ファン化
- 採用活動への貢献
「なんとなく流行っているから」「競合もやっているから」という理由だけで運用していませんか?
目的が曖昧だと、投稿内容がバラバラになり、効果検証もできません。
担当者によって発信内容がブレる原因となり、炎上の第一歩になる場合もあります。
SNSの「担当者」と「運用体制」を決める
「SNS担当が1人だけ」、あるいは「社内で誰でも自由に投稿できる」という状態は非常に危険です。
SNS運用では投稿作成、画像編集、返信対応、改善レポートなど複数の工程が発生します。
属人化するとトラブル時に即対応できず、結果的に運用が止まる原因になります。
また、SNSは“誤解される可能性がある”前提で運用する必要があります。
「企業としての表現にふさわしいか?」「差別・偏見の意図がないか?」「社会情勢とのズレはないか?」など、メインの担当者とは別の承認者による事前チェック体制を必ず設けましょう。
【理想的な運用体制】
- 投稿担当者: コンテンツの企画、作成を行う
- 承認者(上長など): 投稿前に内容をチェックし、公開を承認する
このように複数人の目でチェックするフローをルール化するだけで、うっかりミスや不適切な表現を大幅に防ぐことができます。
なお、すべて内製しようとして疲弊している企業や、一定以上の成果を求める企業は、外部のSNS運用代行会社の力を借りる判断も重要です。
「SNSは無料だからなんとか社内で回したい」と思いがちですが、投稿のたびにネタ出し・撮影・編集・チェック・分析……と時間も手間もかかるため、本業を圧迫する可能性があります。
全社で共有する「SNSガイドライン」を作成する
リスク管理のカギは「SNSガイドライン」にあり。
「作成するのが大変…」と感じるかもしれませんが、このガイドラインが会社を守る盾となります。
担当者が変わっても運用の品質を保ち、全従業員のSNSに対する意識を統一するためのルールブックを作成しましょう。
【ガイドラインに盛り込むべき項目例】
- 基本方針:運用目的、ターゲット、アカウントのペルソナ
- 投稿内容:発信して良い情報としてはいけない情報、企画の方向性
- 表現ルール:言葉遣い、トーン&マナー(例:「ですます調」で統一、絵文字の使用ルールなど)
- 権利関連:著作権や肖像権など画像・動画を使用する際のルール
- コミュニケーション:コメントやDMへの返信ルール(返信する範囲、対応時間、定型文など)
- 緊急時対応:炎上発生時の報告フロー、連絡体制、対外的な発表の担当部署
- 個人利用の注意:従業員が個人アカウントで自社について言及する場合の注意点
【運用“中”編】日々の投稿で絶対に守るべき7つの注意点

日々の投稿は、顧客との大切な接点です。
しかし、一歩間違えればリスクに変わることも。
盤石な土台を築いた上で、実際の運用開始後に意識しておきたい具体的な注意点と、万が一炎上してしまった場合の対処法について解説していきます。
著作権・肖像権・商標権を侵害しない
「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、権利侵害に繋がります。
- 画像・イラスト:
インターネット上の画像やイラストを無断で使用するのは厳禁です。
「フリー素材」と書かれていても、商用利用の可否やクレジット表記の要不要など、必ず利用規約を細部まで確認しましょう。
- 音楽:
投稿に音楽を使用する際は、TikTokやInstagramリールで提供されている公式音源を使いましょう。
フリー素材以外の、CDやダウンロード購入した楽曲を無断で使用すると著作権侵害になります。
- 人物の写真:
従業員やお客様が写っている写真を公開する場合は、必ず本人から許可を得ましょう。
特に、個人が特定できる形で写っている場合は、書面で許諾を得ておくのが最も安全です。
個人情報・機密情報を漏らさない
意図せずとも、写真や動画に重要な情報が映り込んでしまう「うっかり漏洩」が多発しています。
【映り込みチェックリスト】
- PCのモニター画面
- デスクの上や壁に貼られた書類
- ホワイトボードのメモ
- 名刺
- 社員証・IDカード
- 窓の外の風景(場所が特定される可能性)
- 未公開の商品
- 社外秘の資料 など
投稿前には、背景の隅々まで拡大してチェックする習慣をつけましょう。
法令や各SNSのガイドラインを守る
先述の著作権や肖像権以外にも、景品表示法や薬機法、プライバシーなど、SNSには「知らなかった」では済まされない法令リスクが潜んでいます。
特にプレゼント企画、UGC活用、医療系投稿などは専門知識が必須です。
- 景品表示法:
例えば、「日本一」「業界No.1」といった最上級表現や、「絶対に」「確実に」といった断定的な表現は、客観的な根拠がない限り使用できません(優良誤認表示)。
また、広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング」は法律で固く禁じられています。
- 薬機法(旧薬事法):
化粧品や健康食品の投稿で、医薬品と誤解されるような効果効能(例:「シミが消える」「これを飲めば病気が治る」など)を謳うことはできません。
Before/After写真の過度な加工もNGです。
また上記以外にも、SNSによって個別のガイドラインも定められています。
例えば「エンゲージメントベイト=SNSで「いいね!」やコメント、シェアなどのエンゲージメントを人為的に増やす目的でユーザーに特定の行動を促す投稿」が禁止されているなど、それぞれルールが異なりますので、合わせて確認しておきましょう。
差別的・政治的・宗教的な内容は避ける
企業アカウントはあくまでオフィシャルなもの。担当者の個人的な思想や信条を持ち込むべきではありません。
ジェンダー、人種、国籍、思想、信条など、センシティブな話題は避けましょう。
良かれと思った発言が、意図せず誰かを傷つけ、大きな批判を招くリスクがあります。
誤解を招く表現(誤字脱字含む)をしない
誤字脱字はもちろん、言葉の選び方ひとつで、意図しないネガティブな意味に捉えられてしまうことがあります。
特に、災害や大きな事件・事故があった際の投稿は、世の中の空気を読み、不謹慎だと受け取られないよう最大限の配慮が必要です。
例えば投稿前に声に出して読み、複数の人でチェックすることで、誤解の種を摘み取ることができます。
ネガティブなコメントにも誠実に対応する
企業のSNSは一方通行ではなく、“コミュニケーションツール”としての運用が求められます。
コメントを無視したり放置したりすると、「冷たい印象」や「対応が悪い会社」というマイナスの印象につながることも。
最低限の対応ルールやテンプレートを決めておくとスムーズです。
なかでも商品へのクレームや厳しいご意見は、目を背けたくなるものです。
しかし、ここでやってはいけないのが「無視」「コメント削除」「感情的な反論」。
これらは火に油を注ぎ、さらなる炎上を招きます。
ガイドラインで定めたルールに則り、まずは真摯に受け止める姿勢を示し、必要であれば謝罪や事実関係の説明を行いましょう。
公式情報としての一貫性と正確性を保つ
SNSでの発信は、企業としての「公式な発言」です。
自社のWebサイトやプレスリリース、他のSNSアカウントで発信している情報と矛盾がないようにしましょう。
特に、価格や仕様、キャンペーン期間などの誤った情報は、顧客に迷惑をかけ企業の信頼を損ないます。
また、トレンドを無理に追って失敗するケースも少なくありません。
商品の紹介ばかり、社内イベントの報告ばかりなど、ユーザー目線を欠いた“自己満足”な投稿はエンゲージメントが伸びません。かといって「バズってるから」「流行っているから」と、企業らしさに合わないネタを取り入れるのはNG!
ブランドイメージと親和性のある企画かを必ず確認しましょう。
内容の一貫性だけでなく、投稿頻度の一貫性も大切です。
「3日連続で投稿 → 2週間放置」のように投稿頻度が安定していない状態は、アルゴリズム上でもユーザーからの印象においても不利です。
SNSでは継続的に情報発信する姿勢が信用やエンゲージメントにつながります。
かつ、発信し続けることで投稿が“ただの作業”で終わらず、効果測定しやすくなります。
もしも炎上してしまったら?被害を最小限に抑える4ステップ

どれだけ注意していても、炎上の可能性をゼロにすることはできません。
万が一の事態に備え、パニックにならず冷静に行動するための対応フローを頭に入れておきましょう。
STEP1:事実確認と状況把握(最優先)
まずは担当者一人で判断せず、何が、どのように、どの範囲で批判されているのかを客観的に把握します。
感情的な意見に惑わされず、事実(ファクト)を集めることに徹しましょう。
STEP2:ガイドラインに沿った迅速な報告・連携
事前に定めた緊急連絡網に従い、責任者(上長、広報部など)へ速やかに報告します。
対応の遅れは被害を拡大させるため、担当者一人で抱え込まないことが鉄則です。
STEP3:関係部署で対応方針を決定
集めた情報を基に、関係者で今後の対応を協議します。
「投稿を削除するのか、しないのか」「謝罪文を出すのか、静観するのか」「いつ、どのような形で発表するのか」などを冷静に決定しましょう。
STEP4:誠意ある公式声明の発表
謝罪すると決めた場合は、言い訳や責任転嫁と受け取られる表現は避け、何が問題であったかを明確にしたうえで真摯に謝罪の意を伝えます。
今後の再発防止策を具体的に示すことで、信頼回復への強い意志表明が可能です。
まとめ|SNS運用は信頼できるプロに任せて安心

企業のSNS運用には、権利侵害や情報漏洩など多くのリスクが潜んでいます。
投稿前のダブルチェック体制や、法律やモラルに関する知識などが不可欠です。
万が一の際は、冷静な状況把握と迅速な情報連携で被害を最小限に食い止めましょう。
ここまでお読みいただき、「これだけの注意点を常に意識しながら、成果も出す運用を続けるのは難しそう……」と感じられたかもしれません。
社内にノウハウやリソースが十分にない場合は、SNS運用代行サービスの利用がおすすめです。
魅力的なコンテンツを制作するだけでなく、こうした複雑で専門的なリスクマネジメントも含めて、プロに任せられるという大きなメリットがあります。
私たちBEASTAR株式会社は、貴社のブランド価値を損なうことのない「炎上させない」運用ノウハウと、万が一の事態にも迅速に対応できる危機管理体制の構築を得意としています。
日々の投稿チェックから緊急時の対応まで、SNSに関するあらゆる「守り」を固め、安心して「攻め」の運用に集中できる環境をご提供します。
自社の運用体制に少しでも不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
👉BEASTAR株式会社に無料で相談してみる